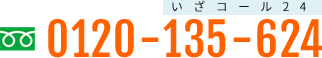- 給水設備の積水工業TOP
- 社員ブログ
- 社長ブログ
- 【コーシャハイム千歳烏山見学日記】
【コーシャハイム千歳烏山見学日記】
平成28年6月7日(火)
【コーシャハイム千歳烏山見学日記】
~多様性で地域をまとめる未来型プロジェクト~
今回、当社も所属する日本建築設備診断機構(通称:JAFIA)のマンション再生部会の
研修の一環として、東京都住宅供給公社(JKK)の団地再生プロジェクトである、
「コーシャハイム千歳烏山」の見学に行きました。
このプロジェクトは、JKKが昭和31年~32年度に建設した
烏山住宅という21棟584戸からなる住宅団地を
建替、再生(改修)、民活(=民間企業の活用)等を活用し、
且つ、地域コミュニティを巻き込む形で再生した大型実験プロジェクトでした。
既存住宅専用団地を一般賃貸住宅、サービス付き高齢者専用賃貸住宅、
地域コミュニティセンター等を併設する、今の時代背景(少子高齢化)にあった複合施設へと再生したのです。
今回の見学会では、特にそのプロジェクトの一部として、
築58年の団地型マンションの再生を実現した建物(建替でなくリフォームもしくはリファイン)を中心に探索しました。
この対象プロジェクトはJKKと首都大学東京の共同開発プロジェクトでした。
その中心メンバー(監修)は日本でも屈指のリファインメーカー、青木茂先生です。
私が感じたこのプロジェクトのキーワードは、次の3つです。
①既存躯体再利用の限界を探る(ストック重視プラン)
②均一型から多様性への生まれ変わり(時代変化への対応)
③設備面の独立性とメンテナンス性の向上(時代の要請)
【①既存躯体再利用の限界を探る】
現在の建築的常識として、RC(鉄筋コンクリート)造の建物寿命は約60年と言われています。
今回対象となった住宅棟は築58年のRC壁式構造です。つまり余命2年しかない建物だったのです。
その建物をあと30年保つ建物として再生する。
しかも単に上塗り 化粧型のリフォームで終らせるのではなく、
今の時代の住民に受け入れられる住形態への変革を同時に実現する。
これは非常に困難な課題だったと思います。建物は人間の寿命と同じで、
全員同じ年齢で人生の終焉を迎える訳ではありません。
それぞれの建物にはそれぞれのメーカーがいて、その時々による体調があります。
けっして同じではありません。建物には、その建物にあった建物再生プランがあるのです。
今回のプロジェクトでは、既存躯体の一部解体と補強(炭素繊維巻き・躯体壁新設等)、
共用廊下部分の新設(S造)等を行い、建物寿命の30年延命に挑んだのです。
【②均一型から多様性への生まれ変わり】
今の時代にあった形とは何なのか?
団地型住居って、皆さんは簡単にイメージすることができますか?
30㎡の2K(和室2室)の住宅が既存の間取りでした。
この基本プランを踏襲した形で、再生しても新たな入居者は確保できるでしょうか?できる訳ないですよね。
私が新婚の時に初めて借りた賃貸アパートは36㎡1LDK(広めの1kかな)でした。
最近の新婚夫婦で、40㎡を切る住宅に住める人はいないでしょ。聞いたことがありません。
均一型大量生産というコスト&量の確保偏重型の住居形態から、
多様性重視の住居形態へ時代は大きく変革しています。
企業等の社宅じゃあるまいし、全て同じ間取りの集合住宅なんて今の時代あり得ません。
どんなにすばらしいプロジェクトでも、実際に利用し続けてもらわなければ、
単なる開発者の自己満足に終わってしまい、空き家を増やすだけです。
今回のプロジェクトでは、サービス付高齢者専用賃貸住宅という用途面の多様性と間取の多様性を持たせる事により、
居住者の年齢構成や、家族人員構成まで変化を持たせることに成功しました。
間取りに関しては、団地型住宅に多い、1階住居の木軸製スラブを解体し、
1階住宅部分のスラブ面を大幅に下げて天井高を確保したり、
既存階段室を利用したメゾネット型住居に変更したり、
通常のリニューアルでは考えもつかない間取り変更を実施しています。さすが青木先生です。
たとえ、新築住宅への建替計画よりもコストメリットが十分に発揮できなかったとしても、
プラン面での優位性は確保する。バリューUPですね。
【③設備面の独立性とメンテナンス性の向上】
躯体部分が30年延命したとしても、設備部分は30年間改修やメンテナンスをしないですむはずがありません。
給湯器やエアコンの寿命も通常は10年~12年です。
エネルギー分野の自由化が今年から始まりましたが、
エネルギー・設備機器・通信機器&制御技術等の変化はこれから激しく起きることが予想されます。
その為に既存設備機器類の機能面に於ける耐用年数も短くなることが予想できますし、
法規制改革の実施もあり得ます。
それらの変化に対し、躯体部分への影響をなるべく少なくした形で対応をする為には、
設備面の独立性と可変性を担保する必要があります。今回のプロジェクトでは、
そういった難しい課題に対しても、様々なアイデアを駆使して、解決に挑んでいます。
設備工事を主体として営業している我々としては、非常に関心が高い部分なのです。
設備用の配管ピットを新たに設けて、設備機器類・共用竪配管をまとめているのです。
住居専有部分内の配管類についても、床下(見えない)に敷設するのではなく、
全てスラブの上で配管をし、設備配管用の乾式壁を新設しました。
その壁さえ撤去復旧すれば、機器類の更新及び配管の更新ができるようにプランニングしてあるのです。
他の住居に影響を与えることなく、設備更新が可能になるのです。
今回の見学会の内容全てをご紹介するのは、
別の機会に致します。若干書き疲れました。
JKKのような公共性の高い団体と、民間企業がコラボして、建物だけでなく、
街全体をリファインするようなプロジェクトがどんどん出てきて欲しいものです。
空き家住宅問題がクローズアップされる昨今、民泊施設を活用しなければ、
インバウンズ需要を吸収しきれないというアンバランスな現象が起きています。
公共施設の中にも利用率が非常に低下している建物も多く存在します。
例えば公立の小中学校です。少子高齢化の波はこれからもずっと続きます。
特に土地代等が高い都心ではなおさらです。
こういったエリアで、公共性の高い建物同士の用途変更を伴う相互利用と
民間企業の活用等を通じて、街の再生プロジェクトを活性化でれば、
面白いことが起きるなあと強く感じた見学会でした。
今回のプロジェクトの概要及び写真等はJKKさんのカタログ(下記PDF)を参照して 下さい。
(写真をクリックすると新しいウィンドウで開き、読むことが出来ます。)
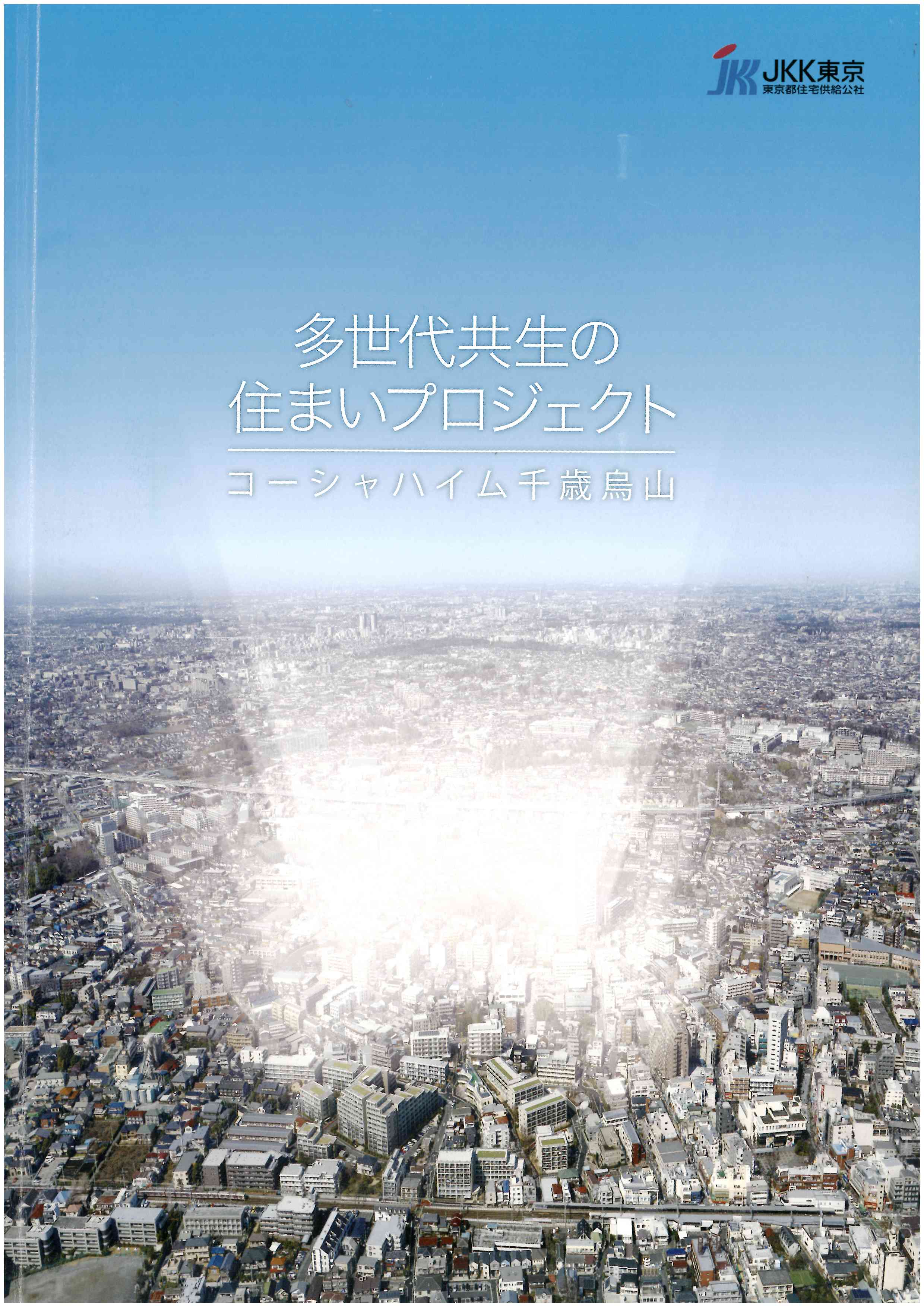
以上
社員ブログ : 社長ブログ
- イベント (63)
- その他 (88)
- 社会貢献 (4)
- 地域活動 (9)
- マンション管理士関連投稿 (9)
- 現場紹介 (8)
- 部活動 (5)
- BCP (2)
- 社長ブログ (77)
- 技術・研修 (60)
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2023年10月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年10月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年2月
- 2014年1月