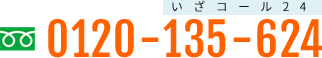- 給水設備の積水工業TOP
- コラム一覧
- 調査・診断一覧
- 飲料水水質検査とは?
飲料水水質検査とは?

飲料水水質検査は、私たちの健康的な日常生活を守る重要な検査です。基本的には水道水を対象として、深刻な健康被害や感染症につながるような有害物質が含まれていないかを検査します。
本記事では、飲料水水質検査の目的や概要、検査項目や数値基準などについて詳しく解説します。オフィスビルの飲料水における水質検査に関しても解説しますので、水質管理に興味がある方はぜひチェックしてください。
目次
飲料水水質検査とは? 水道水の色や細菌の有無を調べる検
水質検査とは、水の色やにおいはもちろん、水に含まれている有害物質や細菌の有無、含有量などを調べ、使用基準に満たしているかを調査する検査のことです。検査する項目や方法は、飲料水や公衆浴場、プールといった対象によって異なります。
飲料水水質検査は、飲料として使われることが多い水道水を対象として行う検査です。飲料水は人体に直接影響を与えるものであるため、特に高い安全性が求められます。有害物質や細菌などが多く含まれる水を飲むと、深刻な健康被害や感染症が発生してしまうケースもあります。
飲料水の水質基準は水道法によって定められている

私たちの生活を守るため、水道水の水質基準は水道法によって細かく定められています。水道法は1957年に成立した法律で、水道の敷設や管理を適正に行うこと、生活環境を向上させることが主な目的です。
水質検査は、水道法の第20条に記載されています。条文によると、水道事業者は厚生労働省の取り決めに従い、定期的に水質検査を行わなければなりません。必要に応じて臨時の検査を行うことも定められています。
さらに水道事業者は水質検査を実施した場合、記録を作成した上で検査日から起算して5年間保管しておかなければなりません。水道事業者は、外部の機関に検査を委託する場合を除き、水質検査を実施するために必要な施設を設けるべきことも記載されています。[注1]
※ここで言う水道事業者とは基本的に公市町村になります
[注1]e-Gov法令検索.「水道法」(参照 2022-08-25)
飲料水水質検査の項目
飲料水の水質検査は、水道法によって定められている項目に従って実施するのが基本です。水道法では、以下のとおり51項目の水質基準を定めています。検査項目と一緒に基準値も確認しておきましょう。[注2]
| No. | 項目 | 基準 |
|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して0.003mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して0.0005mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して0.01mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して0.01mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して0.01mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して0.02mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して0.01mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して0.8mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して1.0mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して1.0 mg/L以下 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して0.2mg/L以下 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して0.3mg/L以下 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して1.0mg/L以下 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して200mg/L以下 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.05mg/L以下 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
| 45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して0.005 mg/L以下 |
| 46 | 有機物 全有機炭素(TCO)の量 |
3mg/L以下 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること |
| 48 | 味 | 異常でないこと |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと |
| 50 | 色度 | 5度以下 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 |
上の表のとおり、色や臭いはもちろん、有害物質ごとに検査項目が細かく分けられているのが大きな特徴です。また、検査項目によって基準値は大きく異なります。一定の数値基準以下であればクリアできる項目もあれば、少量でも検出されるとクリアできない項目もあるため注意が必要です。
[注2]厚生労働省.「水質基準項目と基準値(51項目)」. (参照 2022-08-25)
水質管理の目標値が設定されている項目
前述の表に記載されたもの以外にも、水質管理の目標値が設定されている項目もあります。以下の項目にある物質は、水道水中で検出される可能性がないか、重点的に管理しなければなりません。[注2]
・アンチモン
・ウラン
・ニッケル
・1,2-ジクロロエタン
・トルエン
・フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
・亜塩素酸
・二酸化塩素
・ジクロロアセトニトリル
・抱水クロラール
・農薬類
・カルシウム・マグネシウム(硬度)
・残留塩素
・マンガン
・遊離炭酸
・1,1,1-トリクロロエタン
・メチル-t-ブチルエーテル
・有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
・臭気強度(TON)
・蒸発残留物
・濁度
・pH値
・腐食性(ランゲリア指数)
・従属栄養細菌
・1,1-ジクロロエチレン・アルミニウム
・ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)
オフィスビルで使用される飲料水は建築物衛生法に従って水質検査を行う
オフィスビルなどで使用する飲料水には、建築物衛生法に従って水質検査を実施しなければなりません。検査項目は建物の設備により決まります。貯水槽がある場合は、以下の項目に関して検査を実施します。[注3]
※増圧ポンプのみ設置の場合は不要です(受水槽・高置水槽)
【6カ月ごとに1回実施する検査項目】 ・省略不可項目
・一般細菌
・大腸菌
・鉛及びその化合物
・亜硝酸態窒素
・硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
・亜鉛及びその化合物
・鉄及びその化合物
・銅及びその化合物
・塩化物イオン
・蒸発残留物
・有機物(全有機炭素(TOC)の量)
・pH値
・味
・臭気
・色度
・濁度
【1年ごとに1回実施する検査項目(6月~9月の間)】
・シアン化物イオン及び塩化シアン ※6/1~9/30
・塩素酸
・クロロ酢酸
・クロロホルム
・ジクロロ酢酸
・ジブロモクロロメタン
・臭素酸
・総トリハロメタン
・トリクロロ酢酸
・ブロモジクロロメタン
・ブロモホルム
・ホルムアルデヒド
半年に1回実施すべき検査と、毎年1回実施すべき検査に分かれています。
一部の項目に関して、水質基準をクリアしていた場合は次の水質検査において省略することも可能です。オフィスビルから感染症が発生するリスクもあるため、住宅などと同様、しっかりと水質を管理していくことが大切といえるでしょう。
[注3]厚生労働省.「建築物環境衛生管理基準について」(参照 2022-08-25)
適切な飲料水水質検査を実施して生活環境を維持しよう
今回は、飲料水水質検査の概要や検査項目などについて解説しました。飲料水は私たちの生活に欠かせないものであるため、適切な水質検査により問題がないか定期的にチェックすることが重要です。
基準値を超えた量の有害物質が含まれていたり、臭いや味に異常があったりすると、深刻な健康被害が発生する可能性もあります。水質検査の項目や頻度は、水道法や建築物衛生法によって細かく定められているため、しっかりと理解した上で検査を実施しましょう。